【2025年最新完全版】令和7年分年末調整の大幅改正を徹底解説
基礎控除95万円・給与所得控除・特定親族特別控除の全てを表で分かりやすく解説
令和7年12月1日から年末調整制度が大幅に改正されます。経理・人事担当者、給与所得者の皆様は必ずご確認ください。この改正により、多くの方の税負担が軽減される可能性があります。
📋 目次
1. 改正の全体像と施行時期
令和7年度税制改正により、年末調整に関わる重要な制度変更が実施されます。これらの改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
【表1】令和7年分年末調整の主要改正項目一覧
| 改正項目 | 改正内容 | 対象者 | 最大効果 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|
| 🏛️ 基礎控除の見直し | 合計所得金額に応じて段階的に設定 最大95万円 |
全ての所得者 (低所得者ほど有利) |
+47万円 | 令和7年12月1日 |
| 💰 給与所得控除の改正 | 最低保障額 55万円→65万円 |
年収162.5万円以下の給与所得者 | +10万円 | 令和7年12月1日 |
| 👨👩👧👦 特定親族特別控除の新設 | 19-22歳親族の所得に応じた新控除 | 19-22歳の親族を扶養する世帯 | 63万円 | 令和7年12月1日 |
| 🏠 住宅ローン控除 | 調書方式による手続き簡素化 | 住宅ローン控除適用者 | 手続き簡素化 | 令和7年分から |
通勤手当の非課税限度額が改正される場合、年末調整での追加対応が必要になることがあります。年末調整の前には、国税庁ホームページで最新情報を必ず確認してください。
2. 基礎控除の見直し(最大95万円へ)
基礎控除は、すべての所得者が適用を受けることができる基本的な所得控除です。今回の改正では、合計所得金額に応じて控除額が段階的に設定され、低所得者ほど大きな恩恵を受けられる仕組みとなりました。
2-1. 改正後の基礎控除額詳細
【表2】基礎控除額の改正前後比較(合計所得金額別)
| 合計所得金額 | 給与のみの収入目安 | 改正前 | 改正後(令和7・8年分) | 改正後(令和9年分以後) | 増加額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 200万3,999円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 | +47万円 |
| 132万円超~336万円以下 | 200万3,999円超~475万1,999円以下 | 48万円 | 88万円 | 88万円 | +40万円 |
| 336万円超~489万円以下 | 475万1,999円超~665万5,556円以下 | 48万円 | 68万円 | 68万円 | +20万円 |
| 489万円超~655万円以下 | 665万5,556円超~850万円以下 | 48万円 | 63万円 | 63万円 | +15万円 |
| 655万円超~2,350万円以下 | 850万円超~2,545万円以下 | 48万円 | 58万円 | 58万円 | +10万円 |
| 2,350万円超 | 2,545万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 変更なし |
- 改正後の基礎控除額は、所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額です
- この加算額は居住者についてのみ適用されます
- 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、表の金額と異なることがあります
- 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません
3. 給与所得控除の改正(55万円→65万円)
給与所得控除は、給与所得者の必要経費に相当する概算控除として設けられている制度です。今回の改正では、最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられ、低所得者の税負担軽減が図られています。
3-1. 給与所得控除額の具体的変更
【表3】給与所得控除額の改正前後比較
| 給与の収入金額 | 改正前の控除額 | 改正後の控除額 | 変更点 |
|---|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 | +10万円 |
| 162万5,000円超~180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40%-10万円 | 変更なし |
| 180万円超~190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+8万円 | 変更なし |
| 190万円超 | 従来の計算式 | 従来の計算式 | 変更なし |
この改正により、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されています。年末調整の際は、必ず改正後の表を使用してください。
3-2. 家内労働者等への影響
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
4. 特定親族特別控除の新設
今回の税制改正で最も注目すべき新制度が、「特定親族特別控除」です。これは、19歳以上23歳未満の親族(主に大学生など)を扶養している場合に、その親族の所得に応じて控除が受けられる画期的な制度です。
4-1. 「特定親族」の定義
- 所得者と生計を一にする親族であること
- 年齢が19歳以上23歳未満であること
- 合計所得金額が58万円超123万円以下であること
- 配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者ではないこと
- 児童福祉法の規定により養育を委託された里子も含む
※給与収入のみの場合:年収123万円超188万円以下が対象
4-2. 特定親族特別控除額
【表4】特定親族特別控除額一覧
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入金額の目安 | 特定親族特別控除額 | 税負担軽減効果(概算) |
|---|---|---|---|
| 58万円超~85万円以下 | 123万円超~150万円以下 | 63万円 | 約12.6万円 |
| 85万円超~90万円以下 | 150万円超~155万円以下 | 61万円 | 約12.2万円 |
| 90万円超~95万円以下 | 155万円超~160万円以下 | 51万円 | 約10.2万円 |
| 95万円超~100万円以下 | 160万円超~165万円以下 | 41万円 | 約8.2万円 |
| 100万円超~105万円以下 | 165万円超~170万円以下 | 31万円 | 約6.2万円 |
| 105万円超~110万円以下 | 170万円超~175万円以下 | 21万円 | 約4.2万円 |
| 110万円超~115万円以下 | 175万円超~180万円以下 | 11万円 | 約2.2万円 |
| 115万円超~120万円以下 | 180万円超~185万円以下 | 6万円 | 約1.2万円 |
| 120万円超~123万円以下 | 185万円超~188万円以下 | 3万円 | 約0.6万円 |
4-3. 扶養控除との関係性
【表5】19歳以上23歳未満親族に対する控除制度の適用関係
| 親族の合計所得金額 | 給与収入金額の目安 | 適用される控除制度 | 控除額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 58万円以下 | 123万円以下 | 扶養控除 (特定扶養親族) |
63万円 | 従来どおり |
| 58万円超~123万円以下 | 123万円超~188万円以下 | 特定親族特別控除 | 3~63万円 (所得に応じて段階的) |
新設制度 |
| 123万円超 | 188万円超 | 控除なし | 0円 | 従来どおり |
- 重複適用の禁止:2人以上の所得者の特定親族に該当する場合、いずれか1人の所得者の特定親族にのみ該当
- 配偶者特別控除との調整:配偶者特別控除の対象となる配偶者と重複する場合は、いずれか一方のみ適用
- 相互適用の禁止:親族同士での適用や、控除を受けている親族を特定親族とすることは不可
4-4. 源泉控除対象親族の新設
特定親族特別控除の創設に伴い、「源泉控除対象親族」という新しい概念が導入されました。これは、控除対象扶養親族と、合計所得金額が100万円以下である特定親族を指します。
年末調整で特定親族特別控除の適用を受けるには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。この申告書は、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書との兼用様式となります。
5. 扶養親族等の所得要件改正
基礎控除や給与所得控除の見直しに連動して、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も改正されました。
【表6】扶養親族等の所得要件改正一覧
| 扶養親族等の区分 | 改正前の所得要件 | 改正後の所得要件 | 給与収入のみの場合の目安 | 変更額 |
|---|---|---|---|---|
| 扶養親族 | 48万円以下 | 58万円以下 | 123万円以下 | +10万円 |
| 同一生計配偶者 | 48万円以下 | 58万円以下 | 123万円以下 | +10万円 |
| ひとり親の生計を一にする子 | 48万円以下 | 58万円以下 | 123万円以下 | +10万円 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 48万円超133万円以下 | 103万円超201万5,999円以下 | 変更なし |
| 勤労学生 | 75万円以下 | 85万円以下 | 150万円以下 | +10万円 |
この改正により、より多くの親族が扶養控除等の対象となる可能性があります。特に、パートタイマーやアルバイトで働く配偶者や親族がいる世帯では、控除適用の可否を再確認する必要があります。
6. 年末調整実務の留意事項
これらの改正は年末調整の実務に直接的な影響を与えます。経理担当者は以下の点に特に注意して対応する必要があります。
6-1. 各種申告書の受理と確認事項
-
扶養控除等(異動)申告書の確認
改正により新たに扶養控除等の対象となった親族がいないか確認してください。対象者がいる場合は、「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。提出期限は原則として令和7年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までですが、年末調整時までの提出でも対応可能です。 -
特定親族特別控除申告書の受理
特定親族特別控除の適用を受ける場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。提出期限は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までです。対象者への周知を忘れずに行ってください。 -
基礎控除申告書の内容確認
提出された「給与所得者の基礎控除申告書」に、合計所得金額に応じた基礎控除額が正しく記載されているか確認してください。特に、合計所得金額の計算が改正後の給与所得控除額等を反映したものになっているか注意が必要です。 -
配偶者控除等申告書の見直し
配偶者に給与所得がある場合、改正後の給与所得控除額を適用して算出された合計所得金額に応じて、配偶者(特別)控除額が正しく記載されているか確認してください。
6-2. 年末調整計算の変更点
- 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」:令和7年分から改正されているため、必ず最新版を使用
- 源泉徴収簿の対応:特定親族特別控除に対応していない場合は、余白部分を活用して記載
- 源泉徴収票の改正:特定親族特別控除額等の記載欄が新設
【表7】源泉徴収簿記載例(特定親族特別控除対応)
630,000 円
※1 特定親族特別控除の適用がある場合は、余白部分にこのような欄を設けて控除額を記載する等してください。
※2 特定親族特別控除の適用がある場合は、その控除額を加算してください。
7. 住宅ローン控除の調書方式
令和7年分の年末調整から、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)において「調書方式」が導入されます。これにより、手続きが大幅に簡素化されます。
7-1. 調書方式の概要
調書方式とは、金融機関等が税務署に提供した情報に基づき、国税当局から所得者本人に住宅借入金等の「年末残高情報」を提供する方式です。
【表8】住宅ローン控除の従来方式と調書方式の比較
| 項目 | 従来の方式 | 調書方式 | メリット |
|---|---|---|---|
| 事前手続き | 特になし | 金融機関への適用申請書提出 | 一度の手続きで継続適用 |
| 年末残高証明書の取得 | 金融機関から個別に取得 | 取得不要 | 手続き不要 |
| 控除証明書等の交付 | 税務署から毎年交付 | 税務署から残高情報込みで交付 | 情報が統合され便利 |
| 年末調整時の添付書類 | 年末残高証明書の添付必要 | 添付不要 | 書類準備の手間削減 |
| 交付時期 | 金融機関により異なる | 電子:11月中旬 書面:11月下旬 |
交付時期が明確 |
7-2. 調書方式の留意事項
- 対象者:調書方式に対応した金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出した人
- 証明書交付時期:電子交付は毎年11月中旬頃、書面交付は入居2年目の11月下旬頃
- 添付書類:「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が不要
制度の詳細については、国税庁ホームページの「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」をご確認ください。
8. 令和8年分以後への影響
今回の税制改正は、令和7年分の年末調整だけでなく、令和8年分以後の源泉徴収事務にも継続的な影響を与えます。
【表9】令和8年分以後の源泉徴収事務への影響
| 変更項目 | 変更内容 | 影響範囲 | 対応時期 |
|---|---|---|---|
| 源泉徴収税額表の改正 | 基礎控除の見直しに伴う月次源泉徴収税額の変更 | 全ての給与所得者 | 令和8年1月から |
| 扶養控除等(異動)申告書 | 「源泉控除対象親族」記載欄の新設 | 扶養親族を有する給与所得者 | 令和8年1月提出分から |
| 扶養親族数の算定方法 | 源泉控除対象親族に基づく新しい算定方法 | 源泉徴収義務者 | 令和8年1月から |
| 各種申告書の様式 | 特定親族特別控除等に対応した様式改正 | 該当する給与所得者 | 令和8年分から |
令和8年1月以後に支払を受けるべき給与について提出する各種申告書の様式や記載事項が変更されます。詳細は国税庁の「令和8年分の給与の源泉徴収事務」に関する資料をご確認ください。
9. 具体的な計算例
改正の影響を具体的な数値で確認してみましょう。
9-1. ケース1:年収180万円の単身給与所得者
【表10】年収180万円単身者の税負担比較
| 計算項目 | 改正前 | 改正後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 給与収入 | 180万円 | 180万円 | – |
| 給与所得控除 | 62万円 | 65万円 | +3万円 |
| 給与所得 | 118万円 | 115万円 | -3万円 |
| 基礎控除 | 48万円 | 88万円 | +40万円 |
| 課税所得 | 70万円 | 27万円 | -43万円 |
| 所得税額 | 約3.5万円 | 約1.4万円 | -2.1万円 |
| 住民税額(概算) | 約7.0万円 | 約2.7万円 | -4.3万円 |
| 年間軽減額合計 | – | – | 約6.4万円 |
9-2. ケース2:19歳の子(年収150万円)を扶養する世帯
【表11】特定親族特別控除適用世帯の税負担比較
| 項目 | 改正前 | 改正後 | 差額・効果 |
|---|---|---|---|
| 子の年収 | 150万円 | 150万円 | – |
| 子の給与所得控除 | 55万円 | 65万円 | +10万円 |
| 子の合計所得金額 | 95万円 | 85万円 | -10万円 |
| 親が受けられる控除 | 0円(控除対象外) | 63万円(特定親族特別控除) | +63万円 |
| 所得税軽減効果(概算) | – | 約6.3万円 | +6.3万円 |
| 住民税軽減効果(概算) | – | 約6.3万円 | +6.3万円 |
| 年間軽減額合計 | – | 約12.6万円 | +12.6万円 |
- 年収180万円単身者:年間約6.4万円の税負担軽減
- 19歳の子を扶養する世帯:年間約12.6万円の税負担軽減
- 基礎控除と給与所得控除の両方の恩恵を受けられる低所得者層で特に大きな効果
- 特定親族特別控除により、従来控除対象外だった19-22歳の親族を扶養する世帯でも大幅軽減
10. よくある質問(FAQ)
Q1. 基礎控除は誰でも95万円になりますか?
A1. いいえ。合計所得金額に応じて段階的に適用されます。最も低い所得帯(合計所得金額132万円以下)で95万円、それ以外は88万/68万/63万/58万円など、所得階層により異なります。
Q2. 特定親族特別控除と扶養控除は両方使えますか?
A2. 同一の親族については重複適用できません。親族の合計所得金額が58万円以下なら扶養控除(特定扶養親族)63万円、58万円超123万円以下なら特定親族特別控除(最大63万円)のいずれかが適用されます。
Q3. 住宅ローン控除の調書方式を使うには何が必要?
A3. 対応金融機関に対する「住宅ローン控除の適用申請書」の提出が必要です。以後は税務署から交付される控除証明書等を用い、従来の年末残高証明書の添付が不要になります。
Q4. 給与所得控除の最低保障65万円の恩恵は誰に大きい?
A4. 年収162.5万円以下の方に直接的な恩恵があります。162.5万円超190万円までは新しい計算式が適用され、190万円超は従来どおりです。
Q5. 令和8年以後、源泉徴収事務で何が変わる?
A5. 源泉徴収税額表や扶養控除等(異動)申告書の記載事項が更新されます。特に「源泉控除対象親族」の記載が新たに必要となり、扶養親族数に基づく月次天引き額の算定方法が変更される可能性があります。
11. 出典・参考資料
本記事は、国税庁が公表する令和7年分年末調整関連資料に基づいて作成しています。最新の正確な情報は、必ず国税庁の公式サイトでご確認ください。
- 国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」(変わった点.pdf)
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ」
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm - 国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/index.htm - 国税庁「令和7年分年末調整のための各種様式」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm - 国税庁「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
本記事の表は、国税庁資料の内容を基に編集部が作成したものです。実際の様式・詳細な数値については、必ず国税庁の公式資料をご参照ください。
🔔 最終確認のお願い
本記事の内容は2025年1月27日現在の情報に基づいています。税制は随時変更される可能性があるため、実際の年末調整実務を行う際は、必ず国税庁ホームページで最新情報をご確認ください。
特に重要:通勤手当の非課税限度額改正など、追加の改正が行われる場合があります。年末調整の前には必ず最新情報の確認を行ってください。
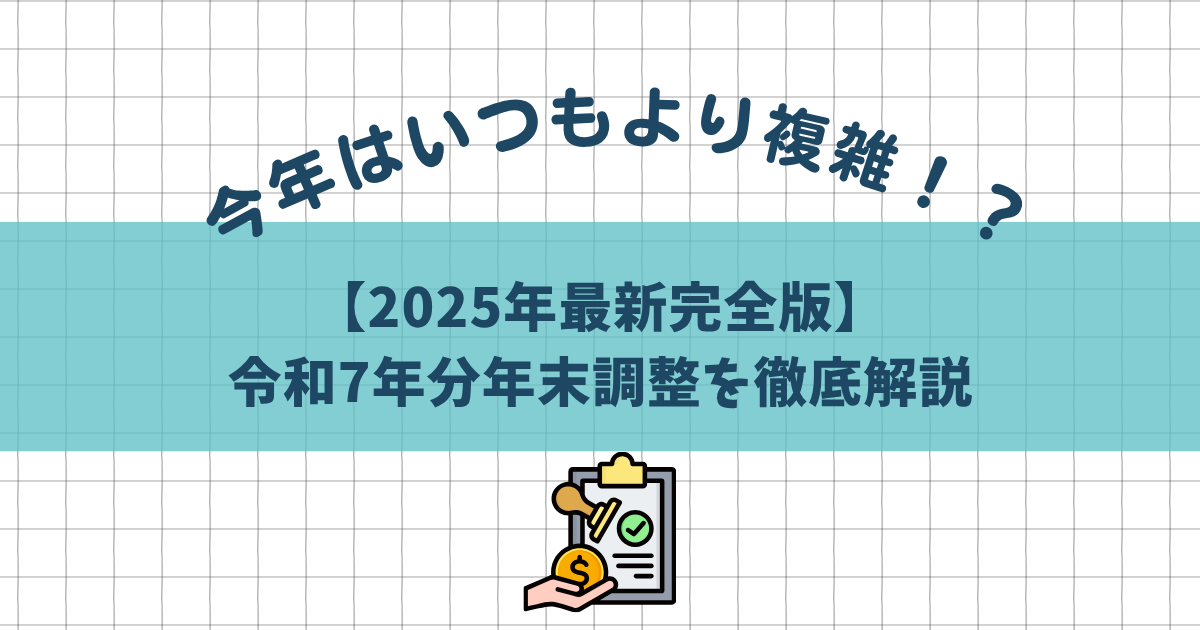
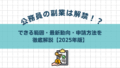
コメント